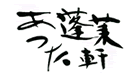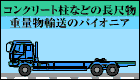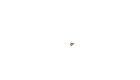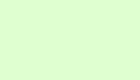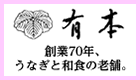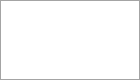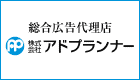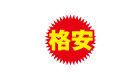2019年6月30日
vol. 141 中村 敬先生「記憶の中の南山の教育(1)」
■戦後発の二つの英語教育論
敗戦直後の1946年(昭和21年)と、その2年後の1948年(昭和23年)に奇しくも同じ
タイトルの二つの英語教育論が出た。一つは福原麟太郎(1894~1981)「英語を学ぶ
人々の為に」であり、もう一つは中野好夫(1903~1985)「英語を学ぶ人々のために」
である。本連載をこの二つの英語論から始めるのは、およそ70年前の英語教育論が
今日においても十分に通用する、いや、ますます光を放っていることを知っておいて
ほしいからである。そうすることで、次回から論ずる南山中学・高校で実践したぼくの
英語教育の意味がよりよくお解りいただけると思うからである。
お二人とも英語教師であるとともに著名な英文学者でもあり、一言ではくくりきれ
ない知的巨人だった。福原さんには『福原麟太郎著作集』(全12巻)研究社、があり、
中野さんには『中野好夫集』(全11巻)筑摩書房、がある。ともに戦前戦後の両時期に
活動された。
お二人とも戦争に協力した。ただし、ぼくの知る限り、福原さんは戦争に対する意思
表示が極端に少ない。戦後になって戦中の身の処し方についてもほとんど語って
いない。その意味で戦争に協力したのだと考える。この点は本稿の範囲外だが、日本の
知識人がどのようにして戦争協力の自己を克服して戦後に到ったのか、その始末を
つけるのは“後継者”の我々だが、依然として始末はついていない。本稿はそれを
目的としていないので深入りできないのは残念だ。本論に戻る。
■Goodbye の意味
福原さんは、『英語を学ぶ人々の為に』の中で次のような趣旨のことを書いている
――、「Goodbye は、Be God with you.(神があなたのそばにいますように→神が
あなたをお守りくださいますように)が訛ったものだ。ここから Goodbye がキリスト
教徒の挨拶だということが分かる」。
イギリスは当時から、そして現在はいっそう多くの民族によって成り立っている
多民族国家である。その意味で、この福原さんのイギリス観は一面的だった。しかし、
福原さんの英語観は一つの国やその国の文化を深く理解するうえで、その国や地域の
ことばを徹底的に学ぶ必要性を説いた点で、決してカビが生えてはいない。戦前戦後期
を通してこの国の英語教育の屋台骨を支えたのがこの英語観だった。ただ、彼には
民族という概念はなかった。その点彼も時代の子だった。
なお、英語教育に関する福原哲学は『福原麟太郎著作集』第9巻(「英語教育論」)
が、その全貌を伝えている。当時健在だった『英語青年』(研究社)に連載した
「英学時評」を今回改めて読みなおしたが、あまりに面白くて読みだしたらやめられ
なくなった。
■すべての英語教師が腰抜けだった
一方、中野好夫さんは次のようにいう――、「その頃(1940年前後、中村注)の
日本の歩みに一番警告や指導を与えなければならない英文学者や英語の先生たちは、
この私をもふくめて、一人の例外もなしに、意気地なしであり、腰抜けであり、
腑抜けであった」(The Youth’s Companion[川澄哲夫編 鈴木孝夫監修『資料 日本
英学史2 英語教育論争史』大修館書店、1978年、所収])。
これは戦後のある時期までは、戦前期の制度などのすべてを否定する風潮の中で
書かれたため、後述するように幾つかの留保が必要だが、本質は今日でも十分通用
する。それは一般論としての英語教師の非政治性である。時の政府を痛烈に批判する
運動の先頭に立つ。こんなことはまずない。理由は、社会的大言語(英語)を習得と
教育の対象としてきたことと無縁ではない。
さて、中野言説の最大の留保点に手短に触れる――。すべての英語教師が腰抜けで
あったわけではない。たとえば、ぼくが小牧中学校(旧制)に入学した最初の英語の
授業で、荒川惣兵衛先生(後に、『角川外来語辞典』1967年、を著わす、1898~1995)
は、開口一番「日本は負けます」といい、時の政府の政策を痛烈に批判した。現在の
ように、発信手段が豊富な時代であれば、黙ってはいなかっただろう。
ぼくが中野さんから受けた影響は計り知れない。しかし、中野さんの戦前から戦後に
かけての思想的変転は、この歳になっても始末をつけられないでいる。死ぬに
死ねない。
■そして、今の学校の英語教育は
当節、ここで取り上げた二つの議論に匹敵する英語教育論は見当たらない。また、
学校の英語教育には思想がない。要するに学校の英語教育にはパラダイム(「典型」
paradigm)がない。あるのは、英語を使える人間を育てるという官と民の欲望だけで
ある。その結果、大学入試の基準となっているセンター試験でのヒアリングの試験は
当然視され、2020年から小学校で英語が正科となる。そしてまた、「英語の授業は
英語で」の官の声は大きくなるばかりである。
しかし、日本人にとって、英語は外国語であって、生活語である第二言語ではない。
今日の英語教育の価値観の転倒の根本的原因はこの一事に収斂される。今日聞き流す
だけで英語が使えるようになると宣伝されているspeed learning や、情報通信技術
(ICT [ Information and Communication Technology] )が提案する方式と学校に
おける英語教育の境界が曖昧になってきた。次回から、ぼくが60年前に南山中学・
高校で実践した英語教育の一端を述べる。それは、パラダイムを喪失した今日の日本の
英語教育への異議申し立てでもある。(了)
*次回「記憶の中の南山の教育 (2)」は、こちら
プロフィール 中村敬先生
英語科の在職期間…昭和30年4月~昭和41年3月
1932年豊橋市生まれ
南山大学英語学英文学科卒業
英国政府奨学生(British Council Scholar)としてロンドン大学留学
主な著書:『イギリスのうた』(研究社)、『私説英語教育論』(研究社)、
『英語はどんな言語か』(三省堂)、『なぜ、「英語」が問題なのか?』
(三元社)、『幻の英語教材』(共著、三元社)、
『英語教育神話の解体』(共著、三元社)など
検定教科書の代表著者:中学校英語教科書The New Crown English Series(三省堂、
1978~1993)、高等学校英語教科書The First English Series(三省堂、1988~1995)